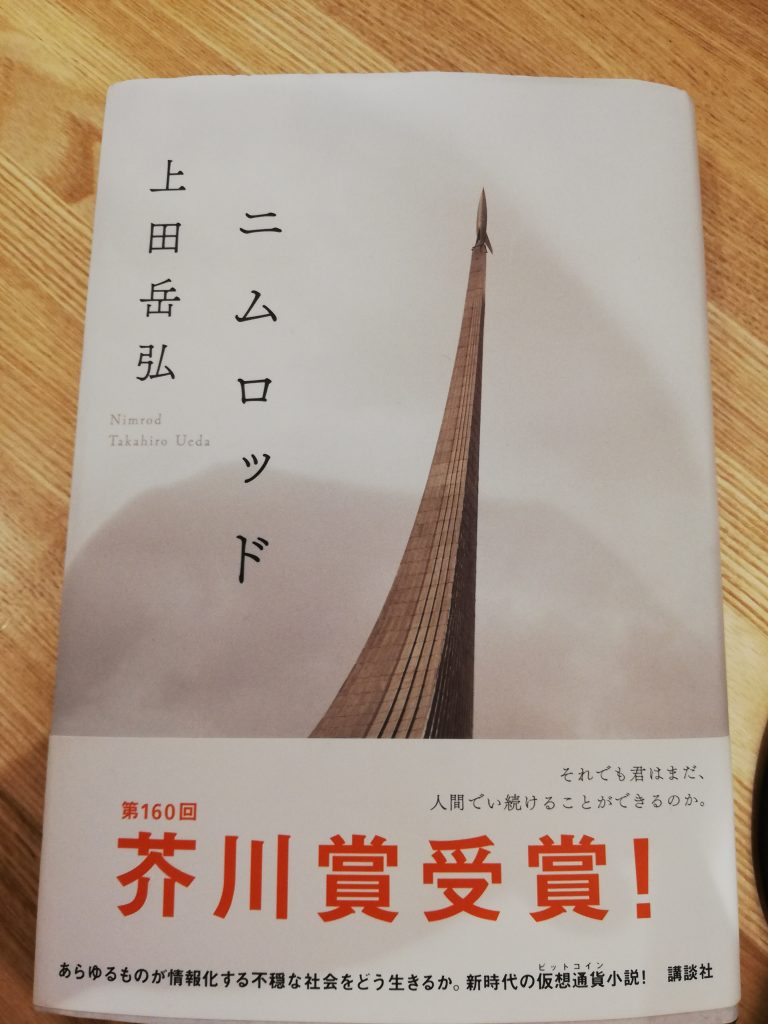書評:芥川賞”ニムロッド”個人が溶けてビットコインへ 著者 上田岳弘
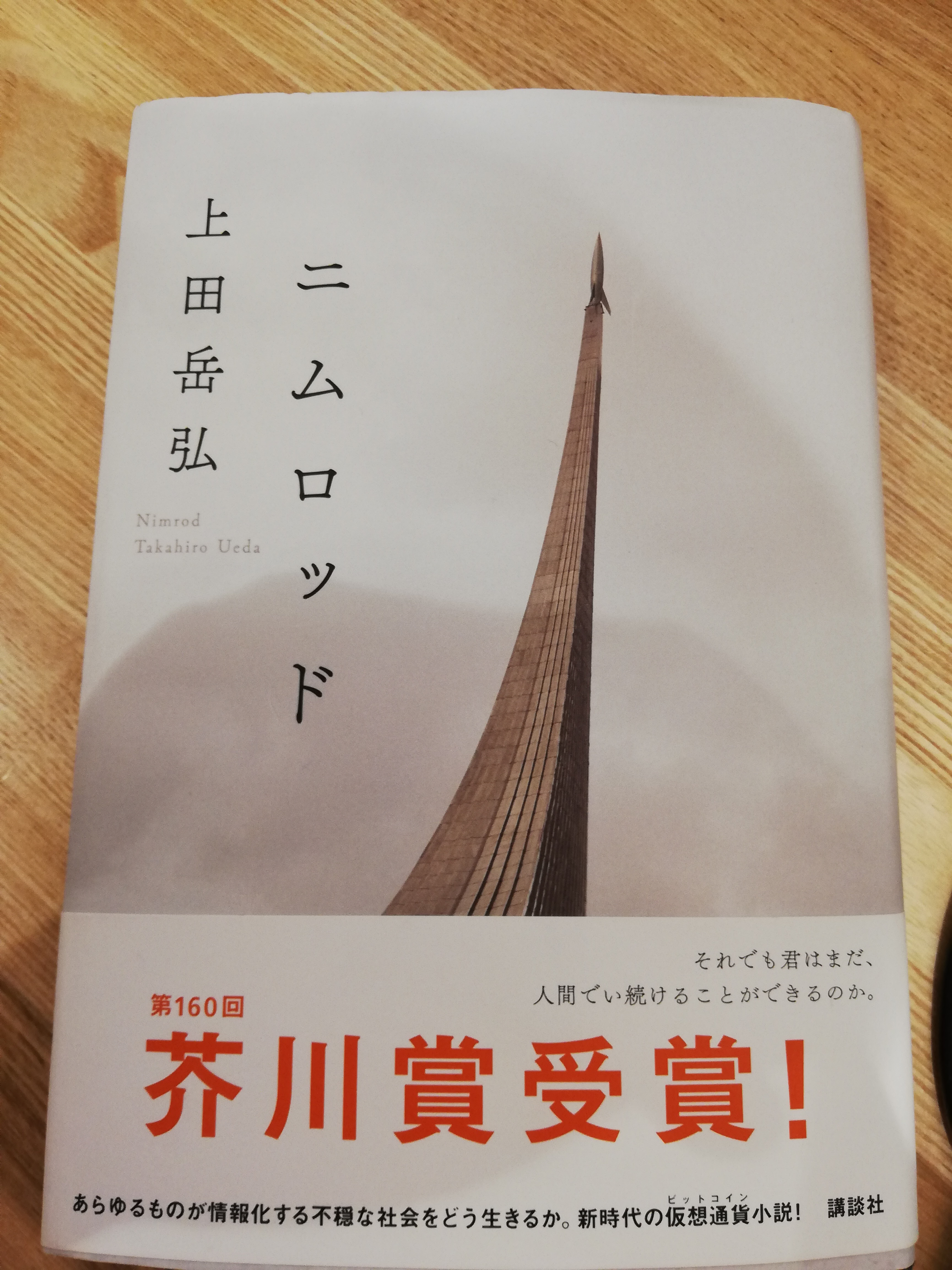
Contents
第160回芥川賞は2作同時受賞でした。
『ニムロッド』著者 上田岳弘(感想を書く方)
『1R1分34秒』町屋良平
ニムロッドを読んで想像したこと
『サピエンス全史』『ホモデウス』『お金2.0』
を読んで、その世界観に沿った小説を書くとこんな感じなのかなと思いました。
著者は『私の恋人』
というクロマニヨン人も登場する小説を2015年に既に書いているため、元々著者は人類史から紬さだれた世界観を持っていた可能性も高いです。
ネタバレなしのあらすじ
主人公の名前は
中本哲史(なかもとさとし、サトシ・ナカモト、Satoshi Nakamoto)
仮想通貨、特にビットコインに興味のある人にとって神の名前である。
ビットコインの最初の設計書であるホワイトぺーバーを作り初期の開発に関わったこと。
ビットコインがそれから10年ちょっと経った2019年の今も運用され、初期は0円で価格もつかなかったものの価値が時価発行総額で一時期は10兆円を超えた。
主人公は中規模のIT企業でデータセンターの管理をしている。
社長に急にビットコインの採掘の部門を作り、社内副業で空いているサーバーでマイニングをすることを命じられる。
同じ会社の同僚で鬱で休職して、復帰して自宅近くで軽めに働かさせてもらっているのが
ニムロッド(本名:荷室)だ。
ニムロッドは主人公に
”駄目な飛行機コレクション”
をメールで送りつづけてくる。主人公がそれに興味があるかどうかなんて関係ないかのように。
でもここにポイントがある。
この主人公は、社会人として適度に周囲に気を使え、社長にも信頼されていることがわかるエピソードが
この小説にはいくつも散りばめられている。
そして同時にこの主人公は、社会から外れてしまったと感じている人が本音を打ち明けることができる貴重な存在としても描写されている。
駄目な飛行機コレクションはニムロッドが興味あるだけだが、それを送り付けても大丈夫な人として主人公は書かれている。
だからもう一人の主要な登場人物
田久保紀子
にとっても、本音を話して大丈夫な存在がこの主人公なのだ。
田久保紀子は、高学歴で外資系の証券会社に勤め30代で中絶をきっかけにした離婚経験がある。
心に負っている傷をこの主人公には素直に見せることができる。
そして、そのような過去があるから、スキンシップはあってもそれ以上ではないような雰囲気で話は進んでいた。
急に田久保紀子がベッドから起き上がるシーンになり、思わずそこから前を読み返してもそれを想像させる部分がない。
これもポイントかもしれない。
あっさりしたように見える関係でもやっている。
駄目だった飛行機コレクションには ニムロッドという対潜哨戒機も含まれている。
飛行機はどれも真剣に夢をもって作られたハズなのに失敗作がいくつもある。それをニムロッドは感情をこめずにメールで報告していく。
ニムロッドは主人公のビットコインのマイニングの話を聴くと即座にそのままでは採掘できるビットコインは段々減っていくはずだと見抜く。
本来賢い人なのだ、それもウツになった一因だろう。
感想
いくつかの話は展開するが、まるでリアリティーがない。
それは小説作るために十分な筆力がないからなのか、
個人がシステムに溶け込む様子を描写して、だんだん個人が薄くなり溶けていくようなぼんやりした感じを表現したかったのか、
よくわからなかった。
この主人公はまともなまま働き続けるのだろう。そして、ニムロッドと田久保紀子は生きる意味も気力もみいだせなくなってシステムの中に消えてしまうのかもしれない。そこには死というできごとすらない、スゥーと消えていくだけ。
賢いこと、類型化できることはシステムに置き換えることができる。それだけの人間はAIに対してメリットを見出しにくい。
人間の変でユニークなそれぞれの個性が持っている部分にのみ比較的長く価値は残存できるのかもしれない。
ただ、組織から個人への世の中の流れは個人でとどまらず、そこから細分化されていき、個人も溶けていくのは必然だ。
例えば、綺麗な景色を見ても自分でそれを感じるよりスマホで写真を撮ってSNSにアップすることに夢中になっている人間はすでにシステムにある部分では取り込まれ、その一部として機能してしまっている。
そういう時代性を感じさせてくれる小説だった。
ネタバレなしでもこれではタイトルが意味不明すぎなので追記
ニムロッドは小説家を目指して落選繰り返したけど今も書いているのです。
そしてみらいにおいては年金運用がビットコインでされていて、人間のはその年金適用を受けるぼんやりした存在になるようなニュアンスがあったので、タイトルをこうしてみました。
この記事をSNSでシェア